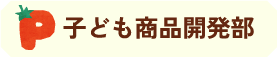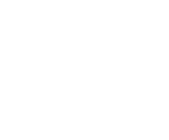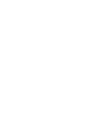子どもの“食べる力”を
育むために、
今できることは?
子どもの“食べる力”を
育むために、
今できることは?
子どもが大人になってから、自分らしく
食事を楽しめるように、幼児期にしっかり
育てたいのが“食べる力”です。
「食べさせる」のではなく、「食べる力を育てる」関わり方とは?
ご家庭で実践できる工夫や声かけのヒントを、堤先生に伺いました。
子どもが大人になってから、自分らしく食事を楽しめるように、幼児期にしっかり育てたいのが“食べる力”です。「食べさせる」のではなく、「食べる力を育てる」関わり方とは?
ご家庭で実践できる工夫や声かけのヒントを、堤先生に伺いました。

子どもが将来、自分で食を選び、健康的な生活を送っていくためには、「食の自立」が欠かせません。その土台となるのが、幼児期に育まれる“食べる力”です。
“食べる力”とは、単に食べ物を噛んで飲み込むといった身体的な機能だけでなく、空腹や満腹といった身体の感覚を感じ取る力、自分の気持ちや食べたいものを言葉で伝える力、食事の場でのマナーや他者との関わり方、さらには食への興味・関心、意欲など、心と体の両面にまたがる力を指します。
この“食べる力”を育てるために、まず大切なのは「食事の時間を心地よく過ごすこと」です。
大人が「残さず食べなさい」「これも食べないとだめよ」といった言葉で無理に食べさせようとすると、子どもにとって食事の時間がプレッシャーやストレスの場になってしまうことがあります。そのような関わりではなく、子どもがリラックスして食事に向き合える雰囲気を整え、食べられたことを一緒に喜ぶことが、前向きな気持ちにつながります。
また、子ども自身が「食べたい」「やってみたい」と思えるような働きかけも大切です。
買い物や料理の場面に少しずつ参加することで、食材や食事への関心が高まります。たとえば、一緒に買い物へ行き「にんじんはどこにあるかな?」と探してもらう、お家で「今日はこれを洗ってみようか」と簡単なお手伝いをお願いする、といった体験が、子どもの自信や意欲を育て、食への主体的な関わりにつながります。
さらに、「食べることは楽しい」「家族と一緒に食べる時間がうれしい」と感じられるような経験を重ねることも、食の自立に向けた大切なステップです。
会話を楽しみながらの食事、旬の食材を味わうこと、一緒に料理をする時間などを通して、子どもの中に食への前向きな気持ちが育まれていきます。
幼児期は、“食べる力”を少しずつ育んでいく大切な時期です。焦らずに、その子のペースを大切にしながら、日々の食事の中でできる小さな関わりを積み重ねていきましょう。
その積み重ねが、将来、自分の健康を自分で守る「食の自立」へとつながっていきます。

◎日本女子大学家政学部食物学科卒業、同大学大学院家政学研究科修士課程修了。
◎東京大学大学院医学系研究科保健学専門課程修士・博士課程修了。
◎保健学博士、管理栄養士。青葉学園短期大学専任講師・助教授。
◎日本子ども家庭総合研究所母子保健研究部栄養担当部長。
◎相模女子大学栄養科学部健康栄養学科教授を経て、2024年4月より現職。
専門は母子栄養学、保健栄養学。「授乳・離乳の支援ガイド」(2019年改定版)策定委員。
-
 【最新号/第14号】2025.7.3
【最新号/第14号】2025.7.3
子どもの“食べる力”を育むために、今できることは? -
 【第13号】2025.4.17
【第13号】2025.4.17
自分の作るご飯で栄養がとれているか心配、確認する方法は? -
 【第12号】2025.3.13
【第12号】2025.3.13
子どもの好き嫌いが違うときの食事準備の工夫 -
 【第11号】2025.1.16
【第11号】2025.1.16
おかずだけ食べて白ご飯を残してしまうことも。ご飯をよく食べてもらうにはどうしたらいいですか? -
 【第10号】2024.11.28
【第10号】2024.11.28
実はおやつには子どもの食事に大切な役割があるのです! -
 【第9号】2024.10.24
【第9号】2024.10.24
季節の変わり目は、体調を崩してしまうことも…熱があるとき、体調の悪い子どもに食べてもらうには? -
 【第8号】2024.9.12
【第8号】2024.9.12
好き嫌いのある子ども。偏食がなくなるにはどうしたらいいの? -
 【第7号】2024.4.18
【第7号】2024.4.18
よく噛んで食べることは、なぜ大切なのでしょうか -
 【第6号】2024.3.28
【第6号】2024.3.28
三色食品群に配慮した献立で栄養バランスのとれた食事を -
 【第5号】2024.2.15
【第5号】2024.2.15
子どもたちに野菜にチャレンジしてもらうための工夫 -
 【第4号】2024.1.18
【第4号】2024.1.18
朝食は、なぜ摂取したほうがいいの? -
 【第3号】2023.12.7
【第3号】2023.12.7
楽しい食卓を囲んで離乳食を -
 【第2号】2023.10.5
【第2号】2023.10.5
「お魚大好き!」な子どもにするには、
どうしたらよいかしら? -
 【第1号】2023.9.14
【第1号】2023.9.14
子どもの食事は、なぜ薄味がいいの?